2025.10.03
今回は、家を建てる前に行う4ステップの最後の行程である「住宅ローンの本審査・着工〜引き渡し」の着工編です。
家が完成するまでは何をしたらいいのか、大まかな流れと、気をつけたい注意点を解説していきます。

家づくりのプランが決まり工事請負契約をし、住宅ローンの本審査も無事通ったら、いよいよ着工に入ります。
これまで数多くの煩わしいことや苦労を経験して「あとは家の完成を待つだけ」と思いきや、実はまだまだやらなければならないことは山のようにあります。
ここからは流れに沿って行うことを紹介していきます。
まず行うのは地盤の調査です。どれだけ建物が頑丈に作られていても、その土台となる地盤が脆ければすべてが水の泡です。そのために行うのが地盤調査です。
家を建てる土地がどんな状態なのか?家を建てても問題ないのか?を調査します。
強い土地と判断されれば問題なく工事を進めるこ とができますが、万が一土地が弱い場合は基礎工事の前に地盤改良を行います。
着工前に近隣への挨拶回りを行います。
建築中は、工事の騒音だけではなく作業車や職人さんの出入り、資材の搬入などで近隣に迷惑をかけることもあります。
トラブルを避けるためにも必ず事前に挨拶回りをしておきましょう。
タイミングとしては、着工前に行う地鎮祭の前後に行くのが一般的と言われています。
どこまで挨拶に行けばいいのか悩みどころではありますが、両隣はもちろん、向かい側の3軒と裏手側の3軒にも挨拶をしておくのが望ましいでしょう。
もし可能であれば、営業担当者や工事責任者にも同行してもらい、工事の日程や騒音が発生しそうな時期を説明してもらうとよいでしょう。
また、挨拶回りをすることで入居後のご近所との良好な関係構築にもつながります。近所の情報等を教えてもらえるだけではなく、防犯や災害などもしもの時に助け合うことができます。
家の工事が始まる直前に行うのが、地縄張りと地鎮祭です。
地縄張りとは、建築予定地に縄やビニール紐を張り、設計図面通りに建物の配置を決めていく作業のことです。
建物の位置を決定する大切な作業になります。隣家や道路との位置関係、駐車スペースなどを確認する大切な行程なので、必ず立ち会って不明点は聞いてみましょう。
一方、地鎮祭とは土地を守る神様に工事の安全を祈願する儀式です。
神主、施主、設計担当、施工担当が立ち会い、その土地の神様に、ここに家を建てることを報告し、工事の無事を祈ります。
地鎮祭の手配は建築会社に任せたり、近くの神社に依頼したりするなどケースバイケースです。
地鎮祭の費用相場は10~15万円が目安です。
神主への謝礼(初穂料または玉串料)は、2~5万円程度が相場で、他に、お供え物の準備費やご近所への挨拶回り用の粗品購入費などが必要になります。
日程は大安など吉日を選ぶ場合が一般的です。希望の日程がある場合は、早めに神主や関係者の方々とのスケジュールを調整しておきましょう。
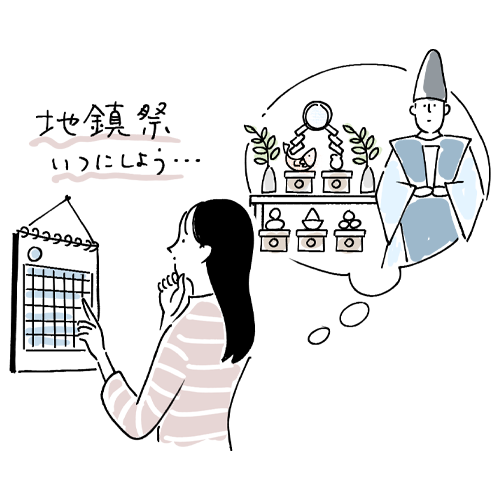
ここからはいよいよ家の着工から着工後の流れについて紹介します。
家の工事が始まったらすべて現場に任せるのではなく、現場の工事見学をして進捗状況を確認します。
可能であれば週に一度顔を出すのが望ましいでしょう。
家が遠いなど頻繁に行けない場合は、「基礎工事・木工事(構造)・設備工事・内装工事・住宅設備設置」など、工事ごとに見学するのも手です。
見学の時間はいつでもいいと言われていますが、極力作業の休憩時間に合わせて訪問し、一段落したところで言葉を交わしましょう。
作業中にむやみに話しかけるのは、職人さんたちの気分を害することもあるので節度を持って話すこと。
実際に建築現場を見て、工事の内容に疑問や当初予定していたことと違う、など問題がある場合は、その場で職人さんに直接話すことは避け、依頼先の営業担当者や現場監督に確認するのが望ましいでしょう。
遠慮せずに気づいた点や気になる点を質問することで、不安感なく進められます。
柱や梁などの骨組みが完成して屋根がかかった、棟上げの段階で行うのが、上棟式(じょうとうしき)です。工事関係者が集まり、工事の安全を願います。
従来は、施主や営業担当者も参加し、宴席を設けるスタイルでしたが、最近では簡単なあいさつ程度ですませ、ご祝儀を渡すだけというケースも。
式を行うかどうかは施主の意向次第になるので、建築会社や家族と相談し、実施する場合は日程を決めてご祝儀の用意や宴会の準備を進めましょう。
工事が終わったら「これで夢のマイホームに住める!」と思われがちですが、実はまだ行うことがあります。それが建物の竣工検査です。
内覧会とも呼ばれ、営業担当者や工事責任者と一緒に建物をチェックします。
床や壁などに傷や汚れはないか、建具の開け閉めはスムーズか、電気の通電や設備は正常に動くかといったことを、担当者に説明してもらいながら確認します。
万が一、不具合や不備が見つかったら建築会社に対応してもらいましょう。
その際、引き渡しまでに修理してもらうのか、入居後に修理してもらうかを相談し、トラブルを防ぐためにも書面に残しておくことを忘れずに。
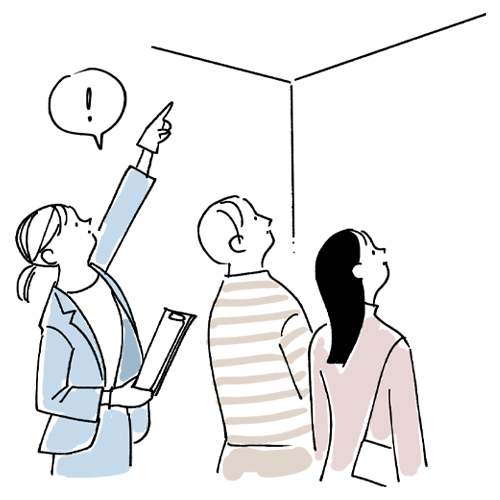
引き渡しまでに直してもらう不具合の修理が終わったら、施工会社が作成した「工事完了書」(建物引渡書)に押印し、いよいよ引き渡しへ。
鍵と保証書、確認検査機関による検査済証を受け取ります。 保証書に書かれている定期点検とアフターメンテナンスについて確認しましょう。